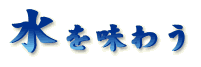 |
 |
| 〜ミネラルウォーターの魅力〜 | |
| 水を美味しく感じる季節になりました。 グルメ&健康ブームなどで、 最近はミネラルウォーターを 日常の飲料水にしていらっしゃる方も 多いのではないでしょうか。 そこで今回はミネラルウォーターの 魅力をまるごとご紹介します。 |
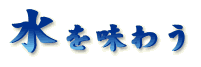 |
 |
| 〜ミネラルウォーターの魅力〜 | |
| 水を美味しく感じる季節になりました。 グルメ&健康ブームなどで、 最近はミネラルウォーターを 日常の飲料水にしていらっしゃる方も 多いのではないでしょうか。 そこで今回はミネラルウォーターの 魅力をまるごとご紹介します。 |