|
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
庶民に愛された素朴でぬくもりのある磁器 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使う楽しみ、盛る楽しみ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
砥石のかけらが器に |
|
|
|
舟上で生まれた生活美 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日本最古の温泉、道後温泉のある松山市から南へ約13km。砥部焼のふるさと愛媛県砥部町は、四国山地を間近に望む温暖で閑静な町です。この地で磁器づくりが始まったのは、18世紀末の江戸時代。町の西方にある砥石山は、その名の通り日本刀や包丁を研ぐ砥石の産地で、砥石のかけら※を再利用するために始まったのが砥部焼なのです。 ※
陶器は粘土(陶土)が原料ですが、磁器は器づくりに適した岩石(陶石)から作られます。陶石として用いるには石英(せきえい)や長石(ちょうせき)などの鉱物成分が含まれている必要があります。器をつくる際はこの陶石を砕いて粉にし、水に沈澱させて作った土を原料とします。砥部焼の場合、初期は同様の成分を含む砥石のかけらを用いましたが、現在はより器に適した陶石を使っています。
|
砥部焼は茶碗や皿などの日用雑器が主体。代表的な器が
”くらわんか茶腕 “です。 ■
砥部焼は手づくり少量生産のため、写真掲載の器もご注文からお届けまで日数のかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
いつもの料理も器を変えたり、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
器の形に合わせた 盛り付けのコツ |
|
|
テーブル全体の印象を変えるには・・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「色々な形の器にいかに美味しそうに盛り付けるか」も大切です。ここでは器のデザイン別にそのポイントを掲げました。また、同じ器を何通りにも使いこなすヒントとして、他のメニュー例(★印)も添えました。参考になさってください。 a.【アイスクリーム皿(めだか)】
フルーツ
b.【切立丸皿(唐草)】
シイタケの肉詰めフライ c.【切立丸皿(赤笹)】
チーズカナッペ
d.【四方曲り鉢(菊紋)】
牛ごぼう ※「牛ごぼう」はあじかん商品です
e.【平片口(呉須赤菊)】
サラダ
|
|
|
「ステキ! 今日はいつもと違う雰囲気ね」 テーブル全体のコーディネートは速効性が魅力。試したその日に嬉しい歓声が聞けるかもしれません。 「器のトーンを合わせる」
センスよく見せるコツは、テーブルに載せる陶磁器の質感を合わせること。陶器なら陶器だけ、磁器なら磁器だけでコーディネートしましょう。 「器の形に変化をつける」
器の形が画一的だと、面白みがありません。お手持ちの丸皿に、長方形・楕円形・八角形・変型(葉形・割山椒など)の器をプラスするか、足付きの器で高さに変化をつけましょう。なお、長方形と楕円形はテーブルで場所をとらず、何かと便利です。 「違う素材をアクセントに使う」
何品かを並べる時、1品は竹籠やガラス器などの異素材を使うとアクセントになります。また、お盆(折敷)やランチョンマットに1人分ずつ並べたり、テーブルクロスを敷いたり、真ん中に花を活けるなどの演出も効果的。グンと華やかになります。
イワシのアーモンドフライ
■材料(4人分)
小イワシ 24尾 卵 1個 ■作り方
シイタケの肉詰めフライ
■材料(4人分)
生シイタケ 12個 ◇衣 ■作り方
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 1999
AHJIKAN CO., LTD.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



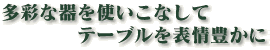

 火の神は煮炊きの始祖!?
火の神は煮炊きの始祖!?