古くから絶えず、未知なる新しい文化の
洗礼をあびつづけてきた港町、博多。
あけっぴろげで、もてなし好き、
新しいモン好きの博多っ子が
「辛いけど旨い」と言わしめ、
育てた明太子を求め、
博多を訪ねる旅となりました。 |
食いしん坊の私は博多の“うまいもん”と聞いて、すぐ明太子を思い浮かべてしまった。ちょっと刺激系のピリ辛風味。何よりあのプチプチした粒の舌触りは一度食べたら忘れられない。
だけど私には、博多と明太子の結びつきにどうしても納得いかないものがあり、その謎を解く機会に恵まれたことに内心、こころおどらせながら博多へと旅立ったのでした。 |

何年ぶりかで訪れた博多の街は相変わらずの賑わいをみせ、都市開発や都市整備の波が今も途絶えることもなく、この街に新しい命を吹きこんでいました。
天神、渡辺通り、中洲界隈を歩いていると目に飛び込んでくるのは、やはり明太子の看板。さすが博多名物“明太子”。
 ご存知のように明太子の原料は「スケトウダラ」。産地は極寒の北海道やアラスカの海。実は、私の疑問はこのことに発していたのです。その地で獲れるものがその地の名産になるはずなのになぜ、博多なの? ご存知のように明太子の原料は「スケトウダラ」。産地は極寒の北海道やアラスカの海。実は、私の疑問はこのことに発していたのです。その地で獲れるものがその地の名産になるはずなのになぜ、博多なの?
ここまで来たら早くその歴史を知りたくて“味の明太子ふくや”さんへと急いだのでした。今年で創業55年を迎える“ふくや”は実は明太子の生みの親ともいえる会社で、創業者の川原俊夫さん(故人)の情熱と探求心がなければ、この明太子は存在しなかったのです。
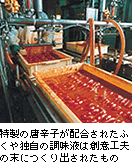 戦後の博多・中洲の一角に小さな食料品店を開いた川原さんの想いは“みんなに喜んでもらえる新しい食べ物”を提供すること。そのヒントになったのが、川原さんが幼年期を過ごした韓国(釜山)で日常食として食べられていた「タラコのキムチ」。この「タラコのキムチ」に着目し、日本人の口に合うよう調味液に工夫を重ね、試行錯誤のうえ試作を繰り返して今の味を完成させたのです。韓国ではスケトウダラを「明太(ミョンテ)」と呼ぶことから「明太(スケトウダラ)の子」、「明太子」と名付けられました。それは昭和24年1月10日のことでした。そう、あの独特の辛味はキムチだったのです。 戦後の博多・中洲の一角に小さな食料品店を開いた川原さんの想いは“みんなに喜んでもらえる新しい食べ物”を提供すること。そのヒントになったのが、川原さんが幼年期を過ごした韓国(釜山)で日常食として食べられていた「タラコのキムチ」。この「タラコのキムチ」に着目し、日本人の口に合うよう調味液に工夫を重ね、試行錯誤のうえ試作を繰り返して今の味を完成させたのです。韓国ではスケトウダラを「明太(ミョンテ)」と呼ぶことから「明太(スケトウダラ)の子」、「明太子」と名付けられました。それは昭和24年1月10日のことでした。そう、あの独特の辛味はキムチだったのです。 |
|
 |
 |
 |

昭和50年、山陽新幹線の博多乗り入れにより「明太子」は全国的に有名になり博多名物として定着しましたが、その陰には、趣味だ、道楽だと冷やかされながらも納得のいく味を探し求め、自ら考案・加味して創りあげた、川原さんの努力があればこそ今があるといっても過言ではないのです。
 街が暮れなずむ頃、中洲や天神ビル街を中心に屋台が立ち並び、街の灯が、人の声が、鮮やかに川面を彩り、昼間の顔とは又別の顔を見せてくれる博多。古くから朝鮮半島、中国大陸、東南アジアへつながる海の街、博多の土地柄が、新しいものに出会い、それを受け入れる、陽性で太っ腹な博多っ子気質を身につけさせたのかも知れません。 街が暮れなずむ頃、中洲や天神ビル街を中心に屋台が立ち並び、街の灯が、人の声が、鮮やかに川面を彩り、昼間の顔とは又別の顔を見せてくれる博多。古くから朝鮮半島、中国大陸、東南アジアへつながる海の街、博多の土地柄が、新しいものに出会い、それを受け入れる、陽性で太っ腹な博多っ子気質を身につけさせたのかも知れません。
ついでにいえば、明太子が生まれたのも、博多人、川原さんに備わった天性の性格が関係しているのかと思え、私の抱いていた疑問は、きれいに消え去ったのです。 |
 |
 |
昼間はクールなオフィス街、夜は川面にネオンを映し、
あたたかい喧噪の場になる中洲 |
おかもと ゆうこ
コピーライター・アートディレクター。広告制作会社代表。
広告代理店博報堂勤務後、フリーの編集者に。企業広報誌や情報誌の紀行文やルポを中心に活動。芸能・文化人等のインタビュアー、CM原稿制作を経て広告制作会社を立ちあげる。
NTTをはじめ、各種企業、ホテルの広報誌等にエッセイを執筆。 |
|



