2000年(平成12年)6月の大手乳業メーカーによる黄色ブドウ球菌・集団食中毒事件から、食品に対する消費者の関心が高まり始めました。
2001年9月(平成13年)には、国内での狂牛病(牛海綿状脳症=BSE)問題が引き起こり、2002年(平成14年)には、原産地表示の偽装事件が発覚し、国の食品行政や食品メーカーに対する信頼が大きく揺らいでいます。
とくに食品メーカーの不祥事に対しては、同じ業界に属するものとして、非常な遺憾をもって接しております。
食品とは何であるのか。今一度、振り返って考えなくてはなりません。本質が失われていると思います。 |

食品という字は、「人を良くする品」と書きます。人々の健康を形成する基本が、凶器になったり、不正にまみれたりすることは、決してあってはならないのです。
常々、社内でも、あじかんの製品に対する思想は、まず何をおいても「安全」であること、そして「正直」であることを訴えております。
これは、生産効率より優先されるべき事項であり、決して忘れてはならないことなのです。これが守られなければ、「退場やむなし」のレッテルを社会から貼られても致し方ないのです。 |
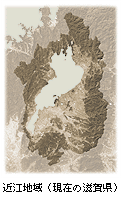 近江商人の経営哲学に「三方良し」という言葉があります。これは、「売り手良し、買い手良し、世間良し」を指しています。 近江商人の経営哲学に「三方良し」という言葉があります。これは、「売り手良し、買い手良し、世間良し」を指しています。
近江商人は、すでにあるモノを買って、動かし、売るだけではなく、地域に入り込み、漁法を改良したり、食品加工に新案を加えたり、その利用法を考案して、産業として興したりと、消費市場の開発にまで及ぶ商いをしていたようです。
つまり、生産者(つくる人)と消費者(つかう人)の間で東奔西走しながら、より安価で必要であるモノが流通するよう、工夫をしていたのです。 |
|
 |
 |
 |
利益が得られるという理由からだけで、行動を起こすのではなく、世間が求めているから、世間のためになるから、という動機づけが必要なのです。
あじかんでも、2001年(平成13年)の正月に、こういった話がありました。
スーパーマーケットに、テナントで出店されたあじかんのお客様が、初めての正月商戦を迎えられ、非常に好調な売れ行きとなり、2日には商材を全て使い切ってしまったそうです。
あじかんの営業担当者は、お得意先の初めての出店でもあることから、「何かあったら、連絡をください」と予め連絡先を、お伝えしていたそうです。
しかし、正月2日の商材の不足です。お客様も駄目で元々と連絡を入れられたそうですが、あじかんの営業担当者は確実に納品を済ませ、決してお客様の手を空かせることは、いたしませんでした。
お客様からは、スーパーに対しても恥をかかずに済んだ、と大変に感謝していただくことが出来ました。このような「お客様が困っていらっしゃることを解決する」ところに商いの原点があると思います。
また、三方良しの「世間良し」とは、あじかんで言えば、消費者を含めた世間の皆様や、地域社会を指しています。
つまり、虚偽虚脱をせず順法精神に則り、社会的な義務や納税を果たすことなのです。社会にとって必要な企業であり続けること、そうでなければ、その企業に存在意義はなくなってしまいます。 |
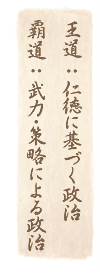 一方で、孟子の唱えた「王道・覇道(おうどう・はどう)」という考えがあります。あじかんが目指すところは、王道であって、決して覇道ではありません。 一方で、孟子の唱えた「王道・覇道(おうどう・はどう)」という考えがあります。あじかんが目指すところは、王道であって、決して覇道ではありません。
一国、あるいは一企業にあって、上の人も下の人も自分の利益だけを考えて行動すれば、その国や企業は大変な危険に陥るでしょう。また、義を後回しにして、利益を追い求めると、結局、他人のものを奪い尽くさなければ、ならなくなります。三方良しの実現もありえなくなります。
西暦で2千年を迎えた現代ですが、紀元前の孟子の教えは、現代にも息づく本質を突いていると思います。 |
|

